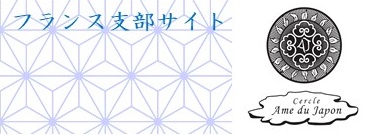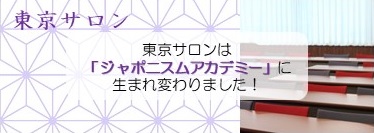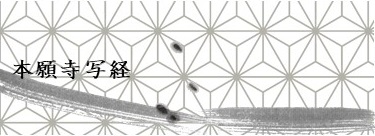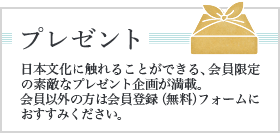高校教育から古典が排除されつつあるという。生産性がない、実社会で役に立たない、それが理由らしい。係り結びは「こそ」だけ文末が已然形になる、下一段活用は「蹴る」の一語しかない、そんな暗記の繰り返しが古典の授業なら、生産性どころか、夢も希望もないだろう。若い世代が嫌いになるはずである。
これとは別に、男女差別の価値観が刷り込まれ害悪である、という主張まであるそうだ。ここまでくると言いがかりも甚だしい。女性の地位が低かったのは、明治の近代化から戦前までの大日本帝国憲法の時代である。それ以前の女性たちは、ずっと自由だった。
平安時代の恋愛は、男性が女性に求愛の和歌を届けることからはじまる。恋文である。無視されたり、はぐらかされたり、選択権は女性にあった。恋仲になってからは、男性は飽きたら通っていかなければよいが、女性の側でも男性を拒否できた。居留守を使ったり、余所に隠れて姿をくらましたりすることがあった。
中納言定頼が小式部内侍のもとを訪れると、誰かが床を共にしている気配がする。西洋なら決闘ものである。今夜は帰ろう、でも自分が来たことはそれとなく伝えたい、定頼はアカペラを唱いながら悠然と去って行く。女は、はっとして、抱かれていた右大臣頼宗の腕をふりほどき、くるりと背を向けてむせび泣いたという。定頼は美声の持ち主であった。あの時ほど恥ずかしいと感じた夜はない、後に頼宗はそう語ったと伝えられている。
往事は一夫多妻制と思われがちだが、必ずしもそうではなく、男性も女性も、複数の相手との恋愛は許されていた。一夫多妻は、水準以上の貴公子か権力者でないかぎり、男性の多くが選別されてあぶれてしまう、むしろ男性側に厳しい制度である。
摂政関白をつとめた藤原兼家には、複数の女性がいた。右大将道綱母も、その一人である。蜻蛉日記で、兼家は「あさましき人」「天下に憎き人」「今日まで音なき人」「恨みきこえたまふべき人」など、散々な言われようである。産後間もない道綱母を見舞いに来ては、別の女あての恋文を置き忘れて帰ったり、「宮中で急用が」と出て行くものの、跡をつけられた行き先が女の家だったり、浮気がばれて閉め出され、家に入れてもらえなかったり、兼家の行動は最低で情けない。道綱母と交わしたプライベートな恋の歌も、四十一首がそのままに明かされてしまっている。今で言うメールやLINEの流出である。
兼家は権謀術数に長じ、最高権力者へと昇りつめていた。どこの国でもいつの時代でも、権力の頂点にいる為政者を向こうに回し、私生活の恥部を暴露することは、少なからぬ危険が伴う。ところが、王朝の女性は表現の自由が保障されていたらしい。大鏡に「この殿のかよはせたまひけるほどのこと、歌などかき集めて、かげろふの日記と名づけて、世に広めたまへり」とある。道綱母が自らの意思で世間に公表し、拡散させていたのだった。
なお、意外に知られていないことだが、王朝特有の複雑な敬語は、和歌では用いない。どんなに身分の差があろうと、男女間でやりとりされる恋の歌は、いわゆる「ため口」、男女は同格であった。
SDGsやLGBTQの横文字を目にする機会が増えた。天皇や上皇の命で編まれる公的な勅撰和歌集は、四季部から始まる。人と自然との共存が季節の移ろいと共に、持続可能な循環型の暮らしに沿った配列で、歌は並べられている。恋部には同性愛の恋歌も収められていた。
時代がようやく古典に追いついたのだ。