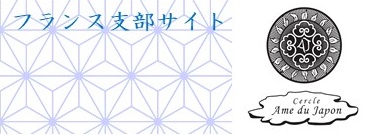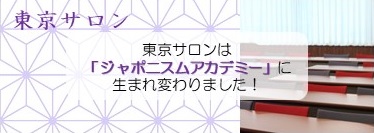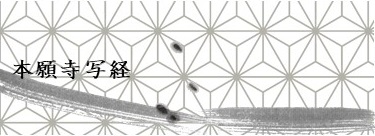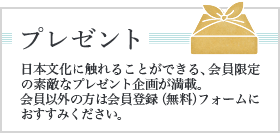JAPONisme Vol.13 – 2017年春
2017年4月1日発行 第13号
CONTENTS
- こころの道標(みちしるべ) 大谷暢順(ジャポニスム振興会会長)
- 風の香り、土の恵み ちょっと、お茶にしましょうか
- 言葉なく、語る 煎茶における非言語コミュニケーション 小川可樂
- 蒼い眼のお茶伝道師 ブレケル・オスカル
- こんなにある! お茶の名産地 茶どころニッポン
- お茶・豆知識 知ると楽しい! ちょこっとコラム
- お茶の魅力を宇治から発信!「お茶の京都博」
- <ご案内>ジャポニスムアカデミー開校!!
- ジャポニスム・六条山通信 花と森の本願寺〈五〉 山折哲雄(ジャポニスム振興会特別顧問)
- 六条山のたから筥 句仏上人『夢の跡』一帖
今号の試し読み:蒼い眼のお茶伝道師 ブレケル・オスカル

日本茶との「苦い」出会い
「日本茶を初めて飲んだのは高校生の時。お茶といえば紅茶しか知らなくて、だから熱湯を使って、たぶん茶葉の品質もあまり良くなくて……。苦かったけれど、それでも、お茶を飲んだ一瞬、まるで自分が山奥の畑の中にいるように感じた──」
そんなふうに当時を振り返るオスカルさん。決して「ひと口でぞっこん、Fall in love」といったようなドラマチックな出会いではなかったが、この東洋の未知なる飲みものは、彼の人生を大きく動かすことになる。
彼の故郷はスウェーデン。幼い頃からシャープのテレビやソニーのステレオ、そして任天堂やSEGAのゲーム機が周りにあって、日本はそれなりに近しい国だった。けれど、とくに興味があるわけでもない。そんなオスカル少年が高校の世界史の授業で明治維新の頃の日本に触れ、感じるところがあって関連の本を探して読み始めるなかで〝侘び・寂び〟の世界に出会う。
「両親が紅茶好きで、自分なりにお茶の時間は大切にしていたし、紅茶や、ほかの国のお茶にもルールやマナーはある。でも、わざわざお茶のために部屋をつくるといった、そんな価値感は知らなかった。これはいったい、なんなのだろう?」
今度は歴史よりもっぱら〝侘び・寂び〟が気になり、関心は茶の湯へ。となれば「抹茶」や「禅」に心酔するかと思いきや、彼は緑茶に惹かれてゆく。その理由は──。
「ひとつには、スウェーデンでは抹茶そのものを味わうことはできても、茶室でお茶を、という環境を得るにはハードルが高かったことがあります。でも、それにも増して、緑茶を飲んだ時に感じた、葉っぱが育った景色を思わせるような山の香り、畑の香りに惹かれて、虜になって……」
いったん哲学を選んだ大学の専攻を「日本語」に変え、さらに岐阜大学へ留学もして、緑茶と、その名産地である日本という国との馴染みを深めていく。
「たとえば人を好きになったら、その人のためにあれもしたい、これもしたい、と思うでしょう。それと同じように、緑茶を好きになればなるほど、いい茶器で、いい水で……と茶葉のために心を尽くしたくなってくるわけです。そしておいしいと思える一杯、そこから広がるゆたかな世界を、色んな人に紹介したくなる。
人生って色々ありますよね。人間であることは大変。生きることはある意味、大変(笑)。けれど、この緑の葉っぱさえあれば、一瞬、精神的にリセットしてひと息つくことができる。たしか千利休の言葉に〝市中の山居〟でしたっけ、周りはどれだけ喧噪にまみれていても、茶室の中でお茶を飲むことによって山に戻れる、みたいな一文があったと思うのですが、一杯の緑茶にも、そんな力があると思うんです。ものすごく平和な境地に瞬間移動できるような……」
斯くして彼は、日本茶インストラクターとなり、国内外に日本茶の魅力を伝える「お茶伝道師」として、今やメディアからの注目度も高まるばかり、なのであるが、そこへ至る道のりは、見目麗しい青年がお茶に惚れ込み、想い想われ……といったような甘いものではなかったようだ。
スウェーデン語はおろか、英語教材も一切なく、もちろん筆記、実技ともに日本語のみで行われる日本茶インストラクターの試験。日本人でも合格率は3割強の難関に、彼も一度は不合格となり「号泣」したことも。お茶を専門職にしたいと思うのは見果てぬ夢なのだろうか、趣味で楽しんでおくべきなのか。
しかしお茶への想いは、その逡巡にまさった。なんと彼は、日本の一般企業への就職を決め、そこで働きながら、再度、試験に挑む。いわく「コテコテの日本企業」での2年のサラリーマン生活は、彼に日本語ばかりでなく「人間としての上達」をも、もたらしたという。
広がる、新たなお茶の愉しみ
「もし良かったら、お淹れしましょうか」エレガントな所作で彼がサーブしてくれるお茶は、これまで飲んできた、どの緑茶とも違う味、香り。
「ちょっと変わってるでしょう? これは香駿(こうしゅん)という品種で、静岡の横沢という山奥の単一農園でつくられているお茶です」
葉だけでなく、花の香りもするようなお茶は、爽やかな苦みと、とろりとやわらかな甘みを口中に広げながら、喉を通ったあとで、もう一度香りたつ。
「ご存じのように、日本茶は〝合組(ごうぐみ)〟と呼ばれるブレンドをされて市場に出るのが一般的。茶商はその技術で、毎年、自然条件が変わるなかでも安定した味と香りのお茶を、安定した価格で提供してきました。けれど最近、ワインのシャトーやウイスキーのシングルモルトと同じような考え方で、ひとつの畑の、ひとつの品質の茶葉だけでお茶に仕上げる、いわゆるシングルオリジンの志向も高まっています」
確かにお茶業界では、老舗の名だたる茶商ほど〝合組〟の技術に誇りを持ち、それぞれにゆかしい「茶銘」を持つ自家の看板商品のクオリティを守ることを矜持とすると聞く。その一方、海外の業者などに茶葉の説明をするシーンでは「ブレンド」=「ピュアでない」と見なされ、その価値がなかなか理解されにくい、という茶商の嘆きを耳にすることも。海外市場にも精通する彼は、そのあたりをどう考えるのだろう。
「シングルオリジンの話を日本の茶商の方にすると、それはごく一部の話だ、とか否定的な意見も多いですけれど……、僕は、地域や品種の個性が際立つお茶はすごく好きですし、外国で日本茶を飲もうという人たちは、やはり、そのあたりにこだわりが強いです。海外に限らず、国内に向けても、茶商の方々が高い仕上げ技術をもってシングルオリジンに乗り出されたらいいと思いますね。従来のブレンドを無くしてというのではなく、たとえばプレミアムセレクションとして。ひとくちにお茶といっても、こんなに違うんですよ、と選択肢を示すことで、日本茶というジャンルを「おもしろいもの」として世間に紹介することができる。それによって、あまりお茶を飲まない世代や、マニアックな人たちにも、お茶の魅力を伝えることができるはず」
そして彼は、蒼い美しい瞳に、ひときわ光を宿らせて、こうも語るのである。
「僕は日本茶との出会いで、人生をゆたかにしてもらいました。最初はその良さを母国やヨーロッパの人々に広めたいと夢みていたけど、今はまず、日本国内でお茶の普及のお手伝いができたら、と思い始めています。日本の「煎茶」のつくり方は本当に独特で、こんなふうに本来の茶葉の持ち味や土地の香りを最大限に活かすお茶がつくられる過程には、多くの先人たちの工夫や文化、ご先祖サマの知恵が詰まっていて、今もまた、進化を続けている。その本場にいながら、日本の人たちがそれを愉しまないのはもったいない」と──。
(すべてのコンテンツがお読みになりたい方は、会員登録後に下記PDFファイルをダウンロードしてください。)
▼以下の画像をクリックいただくとPDFファイルにてお読みいただけます。
※PDFファイルは会員専用のパスワードによって保護されております。会報誌の閲覧を希望される場合は、会員登録手続きのほど、よろしくお願い申し上げます。