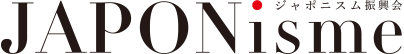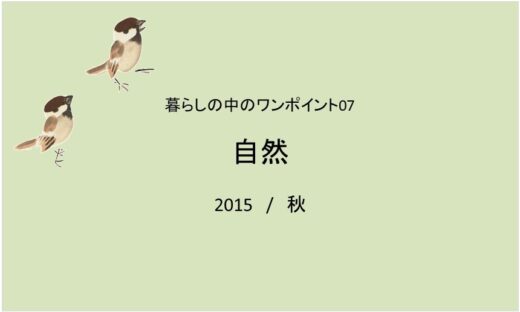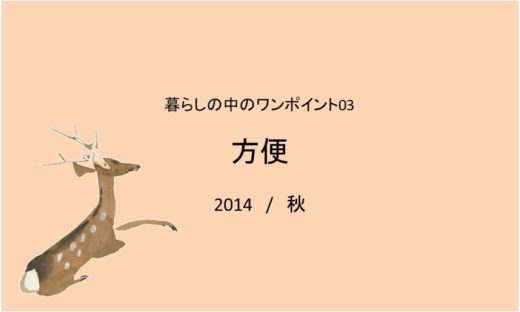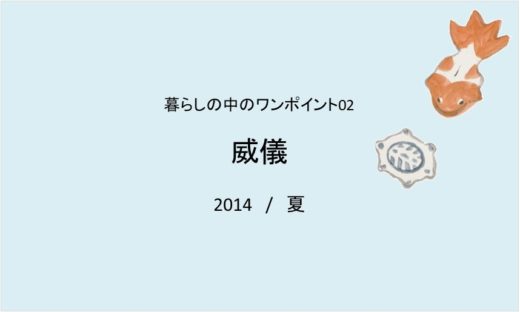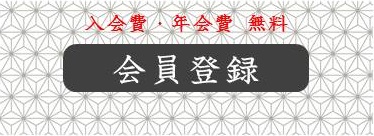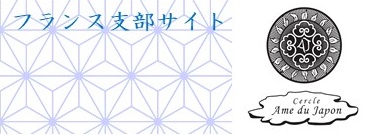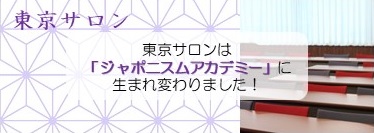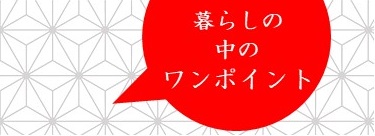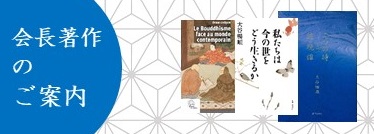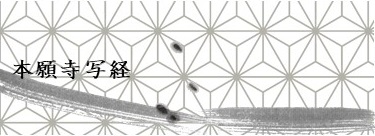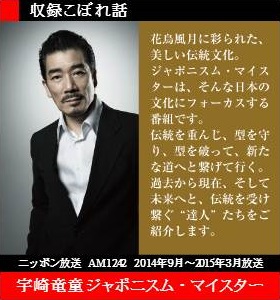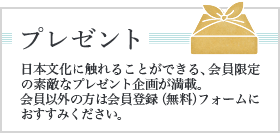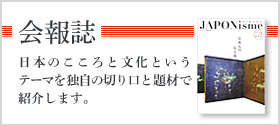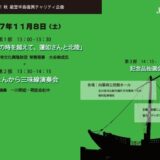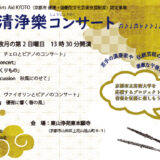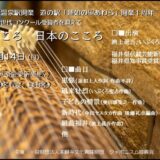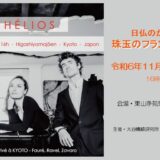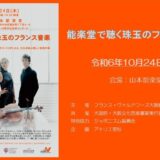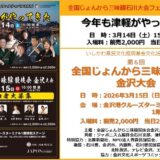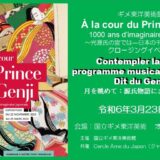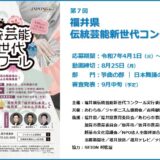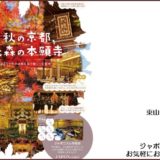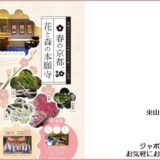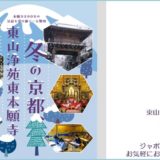縁起 en-gi
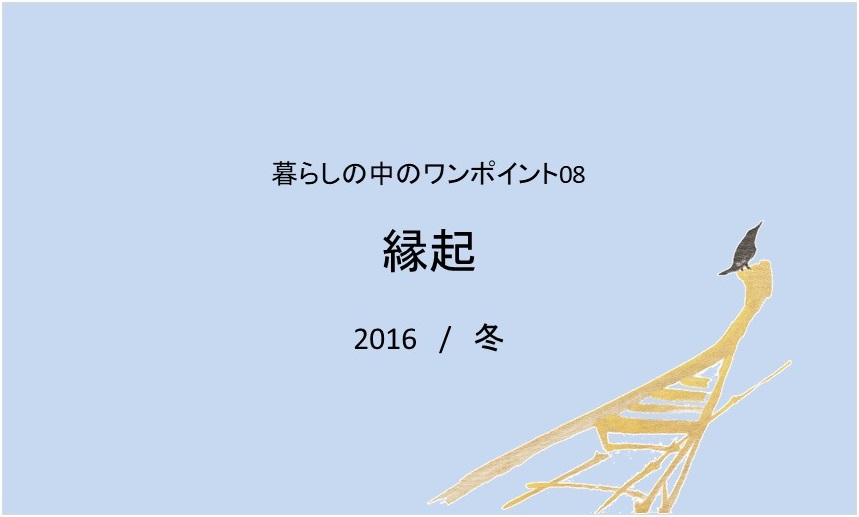
「新年おめでとうございます」。挨拶を交わし、あらたまった気持ちになる正月は、日本人にはやはり特別な日です。食卓には縁起物が並び、初夢に富士山や鷹、ナスを見れば「縁起がいい」などと思われるでしょう。
「縁起」という言葉は、現代では「吉凶の前兆。きざし」という意味で使われることが多いと思いますが、元々の意味は「一切の事象は固定的な実態をもたず、様々な原因(因)や条件(縁)が寄り集まって成立していること」で、仏教の根本思想、「因縁生起(いんねんしょうき)」を二字に略したものです。つまり、すべての事柄はそれ単独で成り立っているわけではなく、なんらかの原因により発生するということです。その意味から派生して、吉兆や良くないことへつながるきざしや、また、事の起こりという意味において、寺社仏閣などの由来という意味でも使われるようになりました。
すべてのものは縁によって起こり、それは我々が生まれる前から絶えることなく続いています。この世界は縁によってつながっているのです。
そのご縁についてピンとこない方は、少し考えてみてください。一人の私には必ず二人の親がいます。その親にもまた二人ずつの親がいます。十代遡ってみると二の十乗で千二十四人もの親がいることになります。それをさらに遡れば・・・・・・。そのうちの一人が欠けても今の私はありません。「有りがたい」ご縁によって今の私はあるのです。
当然のように「有る」と思っている普段の生活。父母や、周りの友人、会ったこともない人々まで、ご縁に生かされて今の自分が「有る」ということを考えれば、違った感覚で景色が見えてくるのではないでしょうか。
それでは、あらためまして、ジャポニスム振興会とご縁を戴いた皆様、本年もよろしくお願い申し上げます。
- 『広辞苑』(岩波書店)
- 『新・仏教辞典 第三版』(誠信書房)