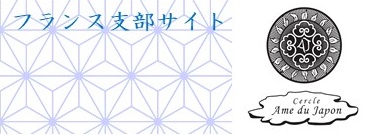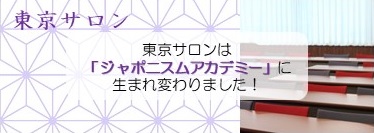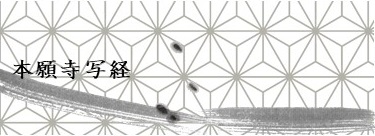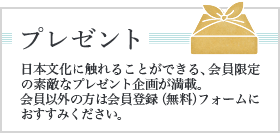花と森の本願寺〈12〉山折哲雄(YAMAORI Tetsuo)

『源氏物語』に姿をあらわす「もののあわれ」と「もののけ」は、いってみれば一卵双生児であり、一心同体だった。
光のあて方いかんで、その相貌はいつでも入れかわる。
ほとんど同じことが、『万葉集』に登場する「相聞歌」と「挽歌」のあいだにおいてもみられるだろう。なぜなら愛(相聞)のうたは、恋し愛する者の死においてこそもっとも深まり、きわまるからだ。
同じように死者への鎮魂の思いは、恋し愛する者への究極の讃歌においてこそ、極上の恍惚、至上の法楽をもたらすだろうからだ。
この愛(相聞)と悲傷(挽歌)のあいだに結ばれるジレンマこそは、千年にわたるこの国の歴史と文化のなかから生まれた「物語」群の、いささかもゆらぐことのない関係だった。
平曲や謡曲、近松や南北の芝居、落語や講談、そして演歌や現代詩の領分でも変ることはなかったのだ。
モノはときにカミになり、オニに変化することがあった。カミのお告げをうけるときは、いつでもモノに憑かれ、モノ狂いになることが予想されていた。いや、期待されていた。
新宗教の開祖が、しばしばモノ狂いになってカミの代理人をつとめるようになったことを思いおこそう。雅びな祭りの舞いが、ときにモノ狂いの踊りに変ずることはよく知られているだろう。
もののあわれはいってみれば心のオモテ顔、それにたいしてもののけは、同じ人たちの心のウラの素顔、もののけを忘れてもののあわれは輝くことができないのだ。同じように、もののあわれを欠くと、もののけは天変地夭をひきおこす。
それが、この災害列島万年の、変ることのないこころのおきてだった。生き抜くための作法だった。
あえていえばその「もの」の複合体のなかから、「物語」というものが誕生したのである。
それは歴史とは違う、縁起とも伝承とも異なる、ある特別の「かたり(騙)」ものだった。