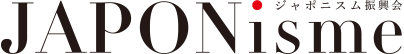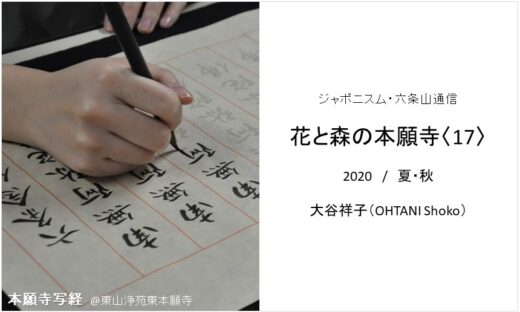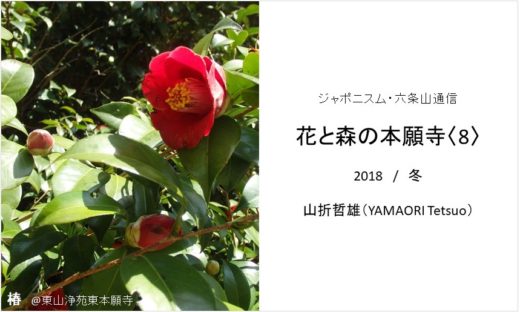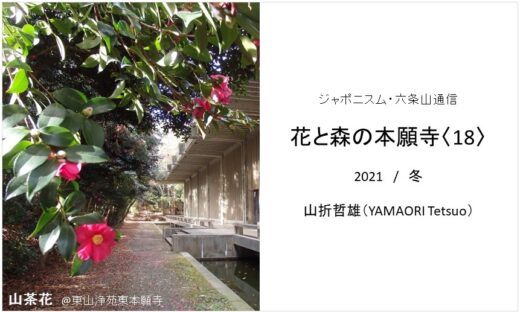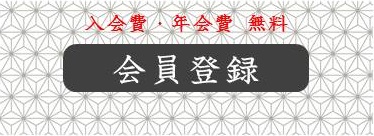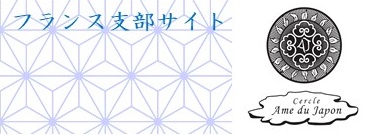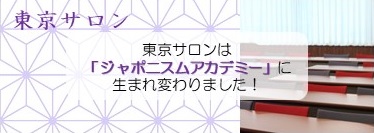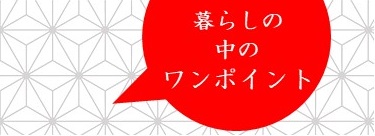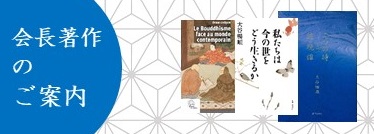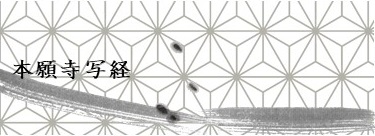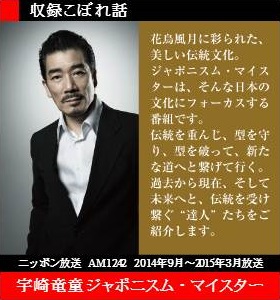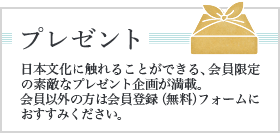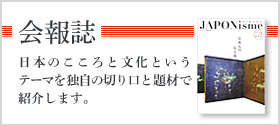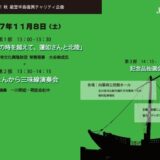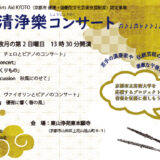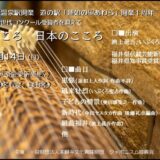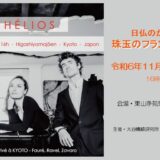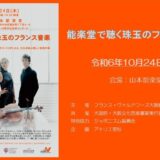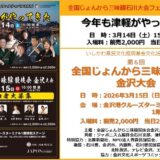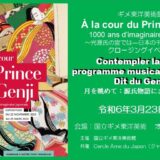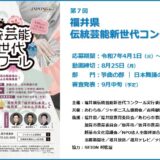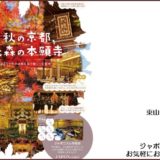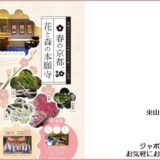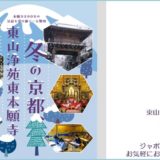花と森の本願寺〈19〉山折哲雄(YAMAORI Tetsuo)
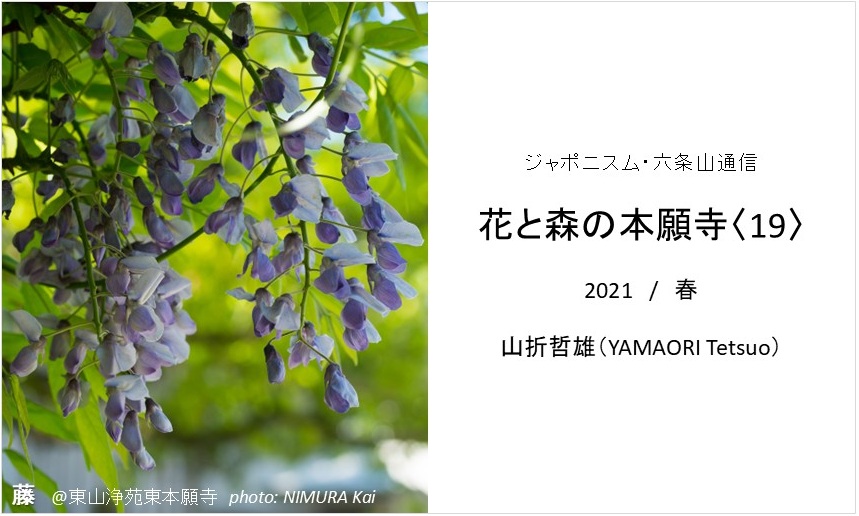
「平成」に移ったころだったと思う。テレビに映る若いタレントさんや女優さんたちの両眼が、みるみる大きく、見開かれていった。
目はぱっちりとキューピーさん、グリグリのまん丸で、今にも飛びだしそう。毎朝やっているNHKテレビの「朝ドラ」のヒロインたちをみていると、それが定番になっていることがわかる。
けれども明治以前は、おそらくそうではなかった。たとえば、「源氏物語絵巻」、そこに登場する姫君たちはすべて、両眼はヨコ一線で、小さな鼻はほとんど片カナのムに近い。つまり引目鉤鼻の手法で描かれている。
この引目は、すでに奈良天平の「鳥毛立女屏風」の美人像にあらわれているから、その伝統は古い。それは時代を降って受けつがれ、江戸時代の浮世絵美人画、その遊女たちの顔を華やかに彩っている。
その引目鉤鼻が、いったいどうしてグリグリ・パッチリに変ってしまったのか。おそらく「明治」になり、ヨーロッパの地中海文明、なかでもギリシャの彫刻や絵画の影響によったのだろう。
ついでにいえば、インドのガンダーラ地方で生まれた仏像たちはほとんどこれまたギリシャの影響をうけてグリグリ・パッチリの眼をしていたが、それが日本にやってくると、ほとんど半眼と引目に近い姿に変貌している。つまりグリグリ・パッチリを追放したのが、そもそもこの国の引目という伝統美の粋だったのだ。
ところがどうしたわけか、「昭和」から「平成」にかけてと思うけれども、こんどは少女、少年たちのあいだで
「かわいい、かわいい~」
というコトバ遣いが流行、それがまたたくうちに大衆文化を席捲していった。その上、この「かわいい」がグリグリ・パッチリ目の少女たちを象徴する国民的な代名詞になっていったのだから、驚かないわけにはいかない。
このごろではそのグリグリ・パッチリ目の少女たちが、こんどは「鬼滅の刃」なるものをふりかざし、何と並いる鬼たちをバッタバッタと斬り殺すマンガが大人気とか、「令和」という時代には、何やら怖ろし気な風が吹きはじめているようだ。