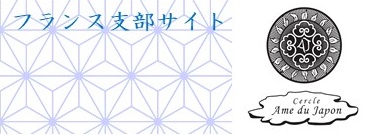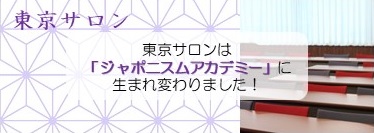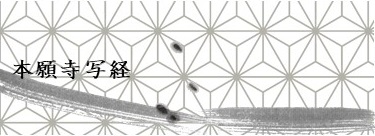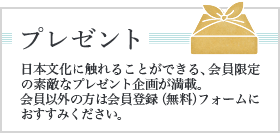学生時代に西宮市に住み、関西学院大学に通っていた私にとって、京都は特別な街で、憧れの人のような存在だった。声をかけたいけれどかけられず、少し離れたところから眺めて満足する。そういう場所だった。その思いは社会人になって東京に移住してからも変わらず、作家になってからはいや増すばかりであった。
けれど小説を書くようになってからは、いつか真っ向から対峙する時が来るのではないかという予感があった。もちろん、京都が私の方へ歩み寄ってくれるはずはなく、私から近づかなければならない。つまり小説の舞台として京都を選ぶのである。そうとなれば中途半端なことは書けない。相当な取材をする必要がある。でもどうやって? と、もじもじしているうちに、ついにそのチャンスが訪れた。「異邦人(いりびと)」というタイトルのその物語は、京都の美に魅入られた女性が主人公である。京都在住で、当時関西学院大学の教授を務めておられた阪倉篤秀先生が取材の入り口を作ってくださった。実に様々な京都関係者にお目にかかり、取材をしていくうちに、中京区在住の建築家、瀬戸川雅義さんの知己となった。瀬戸川さんに「京都の一番深いところを取材したいのですが」と相談すると、「それなら、僕が通っている和歌会に参加なさいませんか」と誘ってくださった。それが冷泉家和歌会への入門のきっかけとなった。
当初、冷泉家と聞いて私は縮み上がった。冷泉家歳時記をテレビで見たことがあったし、国指定の重要文化財である冷泉家住宅の前は何度も通ったことがある。重厚な構えの門の奥にはどんな世界が広がっているのかと、学生時代に今出川通りを歩きながら想像を膨らませたりもした。その冷泉家へ足を踏み入れる日が来ようとは。
緊張する私に、冷泉貴実子先生は温和な笑顔でやわらかく語りかけてくださった。「取材もよろしいけど、和歌を詠んでみはったら、もっとええと思いますよ」その一言に導かれて参加を決めた。
入り口から奥へ奥へと美しい襖で仕切られた御座敷をいくつか通り過ぎて、庭に面した一間が教室となっていた。生徒の皆さんは広間に向き合って正座し、上座に貴実子先生が座して、毎月の題の解説をしてくださる。そして、参考となる和歌を皆で声を合わせて披講する。墨をすり、毛筆で短冊に和歌をしたためる。
私にとって和歌の創作は初体験で、墨をすって毛筆を使うのは小学生の時以来だった。最初はまったく筆運びがままならず、一首詠むのにずいぶん時間がかかった。けれど「和う歌たを詠む」という行為に、私は不思議なほど熱中した。そこには創作の原点があり、日本人の心に響く言葉の数々があった。和歌の真髄を一生かけて追求したいと、私はいつしか思うようになった。
和歌のおけいこに通い始めて早や八年が経つ。数年前からは日仏を往来するようになって、月に一度の楽しみな例会にもなかなか参加できなくなってしまった。それでも京都に、冷泉家に行く日は心が沸き立つ。しんと澄み渡った教室で和歌を詠む、その愉しみはどんなことにも勝る。一生かけても追いつけないかもしれない。それでもやはり、追いかけたい。憧れの人の背中をみつめ、そっとついていきたいと思っている。