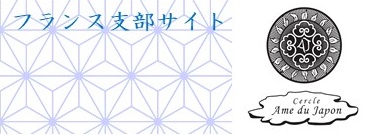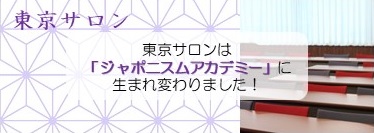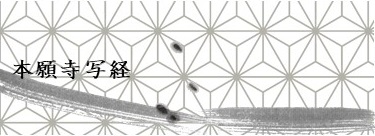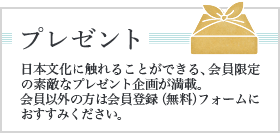花と森の本願寺〈11〉山折哲雄(YAMAORI Tetsuo)

明治になって、西欧の近代語が導入され、それで新しい日本語がいろいろつくられるようになった。福沢諭吉や夏目漱石がやった、工夫や苦労話が伝えられている。
ところがその明治の改元から150年もたてば、それらの新造語の現在にもさまざまの風雪のあとが刻まれているのは当然だ。
たとえば、日本人の一般的な感覚になじむ言葉もあれば、そうではない言葉もあるだろう。翻訳がうまくいった場合もあれば、いつまでもぎくしゃくして衝突してばかりいる場合もあるだろう。成功した造語、一敗地にまみれた言葉、いろいろあるにちがいない。
それ自体は何も日本だけにかぎらず、後発の近代化にのりだした文化圏ではおなじみの、どこでも経験していたことだ。
その近代的な日本語のなかで、新造語のほんやく移植に成功した例として
個人 自由 独立
などを挙げることができるだろう。これにたいして失敗した、もっとも際立っている言葉が
宗教
という造語だったのではないか、と私は長いあいだ考えてきた。
「宗教」をあらわす元の言葉は、いうまでもなく「レリジョン」だった。ここでその語義解釈にふれる必要はないが、両者の食い違いをひと言でいうと、新造語の「宗教」は、日本人の「こころ」の領域を、全体的にカバーすることがついにできなかったということだ。
ところが日本語の「こころ」は西欧語でいう「宗教=レリジョン」はおろか、道徳が芸術の領域までを包摂する、より広い、より深い世界をあらわす独自の言葉だったのである。両者を並べたときに生ずる、いうにいわれぬ違和感の原因がまさにそこにあったと私は思う。
それだからわれわれはその両者のあいだの食い違いを埋めるために、たんに「宗教」とはいわずに「宗教心」といい、「道徳」という言葉とともに「道徳心」という表現をいつでも大切にしてきたのである。