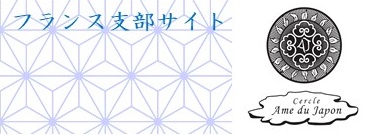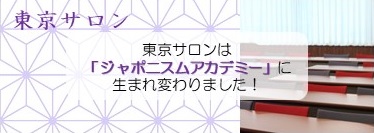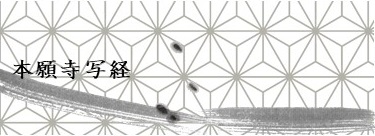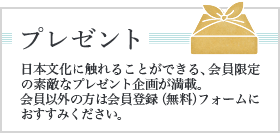花と森の本願寺〈16〉山折哲雄(YAMAORI Tetsuo)

今、この国で流行りだしているジャパン・ブルー、そのことを耳にして反射的に脳裡にひらめいたのが藍染めの青ではなくて、斎藤茂吉の第一歌集『赤光』の赤だった。
のど赤き玄鳥ふたつ屋梁にゐて
足乳ねの母は死にたまふなり
とにかく茂吉は赤が好きだった。そのことがよくわかる。
ところがその茂吉とふるさと(山形県)を同じくする藤沢周平の長編『白き瓶‐小説‐長塚節』を読むと、作者が根っからの「白」好きだったことが伝わってくる。
茂吉は「アララギ」の世界を威風堂々と歩いていったが、長塚節は結核を病み、旅から旅の生活にわが身をかりたて、三十七歳の短い生涯を終えている。『白い瓶』のタイトルに印象深く刻まれた白が、私には死装束の白、喪に服する白にみえてきたのだ。
白埴の瓶こそよけれ霧ながら
朝はつめたき水くみにけり
このように茂吉の赤、藤沢周平の白と連想が飛べば、ブルーの風はどこから吹いてくるだろうか。自然にわが頬にふれてくるのが、あの宮沢賢治の『春と修羅』のなかでつぶやかれている、妖気をはらむ言葉だった。
いかりのにがさまた青さ
四月の気層のひかりの底を
唾し はぎしりゆききする
おれはひとりの修羅なのだ
東北ブルーの青である。底無しの孤独の中、その自己認識の青である。
ふと、『仏説阿弥陀経』の一節が蘇る。「…青色青光黄色黄光赤色赤光白色白光…」、浄土の世界に輝きわたる美しい光をうたった詩句であるが、その浄土にも修羅の巷がまぎれこんでいたのかもしれない。