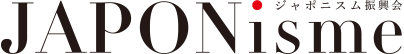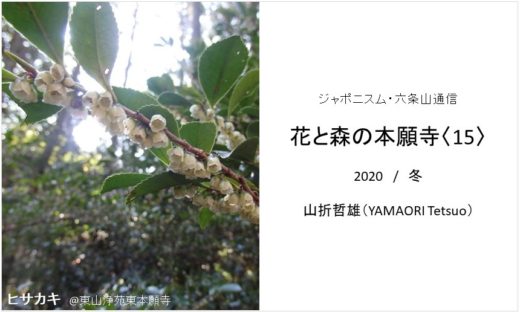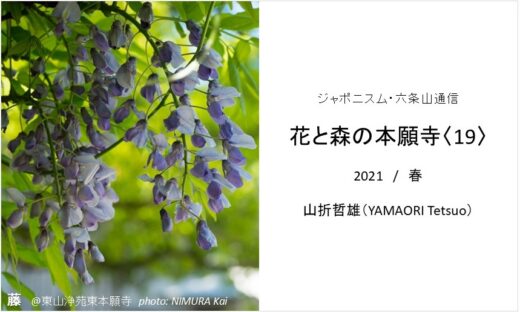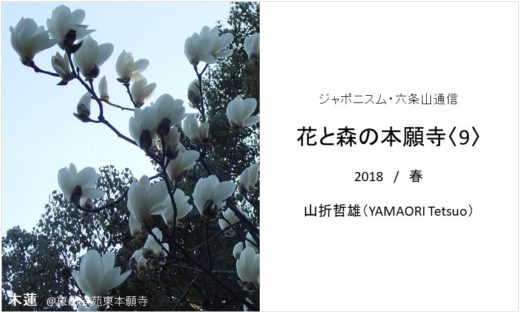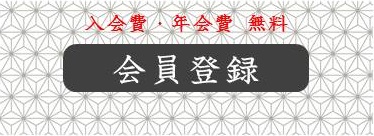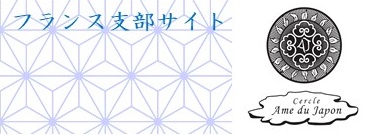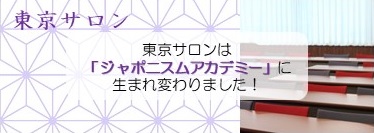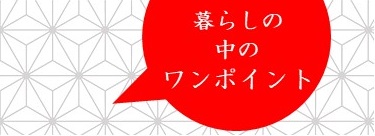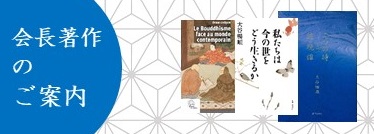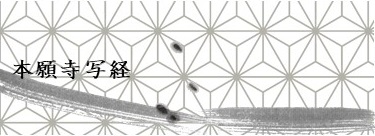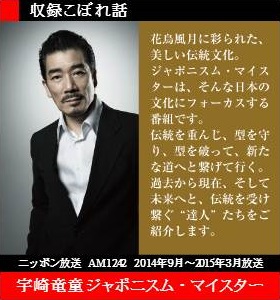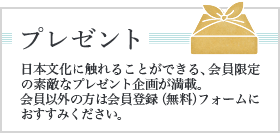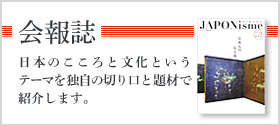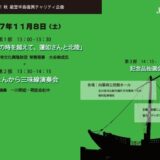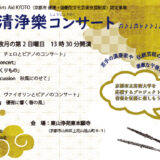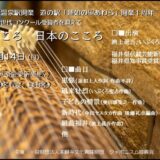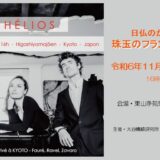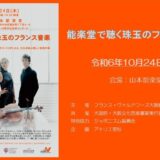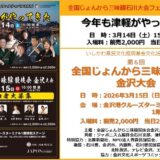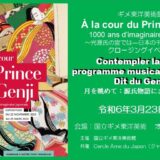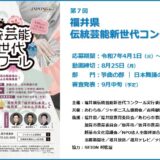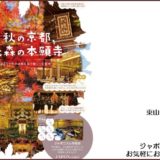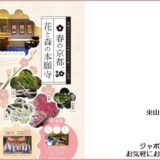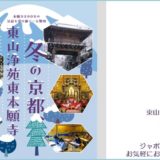花と森の本願寺〈18〉山折哲雄(YAMAORI Tetsuo)
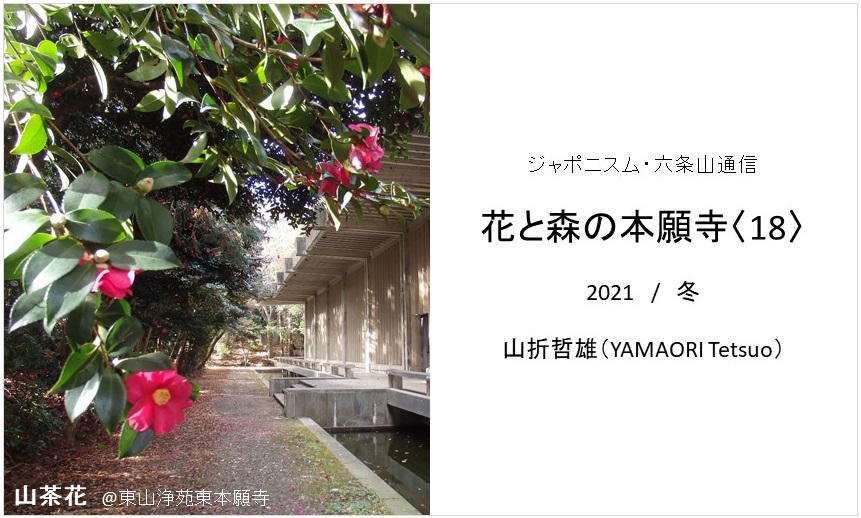
昨年(2020年)の暮近く、昭和の名優・坂田藤十郎さんが亡くなった。89才、どういうわけか、私と同年だった。
生前、一度だけお目にかかったことがある。大阪の歌舞伎座だったかと思うが、その楽屋でお話をうかがった。
同じ昭和6年生れだから、ともに旧制中学の二年坊主ぐらい、半分はまだ軍国少年、あとの半分は戦後生まれの民主主義少年、話はそんなところからはじまったように思う。
歌舞伎のことは何も知らなかったが、ただ上方歌舞伎が市川団十郎さんの江戸歌舞伎とはまるで違う味わいのものであることに興味をもっていた。
ずい分以前のことになるが、藤十郎さんがまだ中村扇雀を名乗っていたころ、心中ものの舞台をみていて、ハッと思うことがあった。その身ぶり手ぶりが、どこか文楽人形の仕草に似ていたからだ。
人形が、目に見えない糸に操られるように動いている、その姿かたちが中村扇雀のからだそのものの動きに重なったのである。もっとも、それを運命の糸に操られる技かとまで思ったわけではないが、はじめての印象はそれに近いものだったような気がする。
舞台における藤十郎さんの動きは今も昔も、つまり扇雀時代から変らないが、ふと腰を動かして立ち姿になり、よろよろと歩きだして、つと止まり、また腰を落とす。その一連の動きの流れに、ある固有のリズムのあることに気づいたのである。
言葉にすれば身も蓋もないことになるが、それが五七五七七の、静かな律動感だった。五で立ち上り、七五で上体がゆらりと傾き、七七で色気のにじみでる下半身を沈める。和歌のリズムになっている、と思ったのだ。
そういえばさきの対談の冒頭で藤十郎さんは、上方歌舞伎の要所は音楽ですよ、といっておられた。出所はもちろん、義太夫節のことだろう。
そうなれば、市川団十郎さんによる江戸歌舞伎の「勧進帳」などは、どう考えても和歌の下半身を斬り捨てた、俳句の気迫がこもるリズムだよなあ、の感慨がわく。